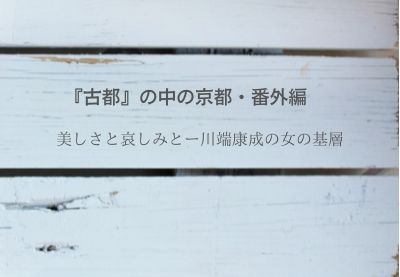
美しさと哀しみとー川端康成の女の基層
美しい。でも哀しい。花のように笑う薫、島村に染まってゆく駒子、ふた子でありながら生き別れ、偶然の再会で出会うものの、別れ道を選ぶ苗子がそうである。それだけではない。彼が作り出す数多くの人物には妙な寂しさ、悲しさ、その上冷たさが入っている。おそらくこれは作家自身の自画像であろう。
悲しき家系
その中、特に一貫しているのはヒロインである女性の描き方である。川端康成は悪女のような女さえ純粋で清潔な視覚を堅持している。また外面から見れば、綺麗さという観念は単なるものではなく人物の性格と精神が結びつけて、人物の底から出る神秘に近い美しさを発する。しかし川端康成は世間で非難を浴びるはずの女であっても、悲しさと淋しさを加えてはっと映える一瞬を綺麗に取り上げる。おそらくそこには川端康成の家系に流れる運命の血縁のつながりの影響もあると思われる。
川端康成は母親の二度目の結婚で生まれた命である。さらに母親の一番目の結婚の相手は自分の父親の兄であり,まるで運命のようにそれはすでに祖父の代からあったことである。川端康成を育ててくれた祖父である三八郎は黒田家のタカと結婚するが、タカが恒太郎を残して二人目の出産で亡くなり、その後妹であるカネと再婚して川端康成の父親である栄吉を産むのである。祖父の姉妹との結婚は母親の兄弟との結婚に繰り返すのだ。
川端康成が求めた清潔な女性観や結婚というものに対する認識には、おそらく川端康成家系の影響があったと言っても無理ではないだろう。
その中、特に一貫しているのはヒロインである女性の描き方である。川端康成は悪女のような女さえ純粋で清潔な視覚を堅持している。また外面から見れば、綺麗さという観念は単なるものではなく人物の性格と精神が結びつけて、人物の底から出る神秘に近い美しさを発する。
しかし、川端康成は世間で非難を浴びるはずの女であっても、悲しさと淋しさを加えてはっと映える一瞬を綺麗に取り上げる。おそらくそこには川端康成の家系に流れる運命の血縁のつながりの影響もあると思われる。
川端康成は母親の二度目の結婚で生まれた命である。さらに母親の一番目の結婚の相手は自分の父親の兄であり,まるで運命のようにそれはすでに祖父の代から始まったのである。